リモート時代に感じる職場の「距離感」
~ホノルル在住の私が感じた変化のリアル~
私が働くホノルルでも、パンデミック以降、リモートワークが当たり前になりつつあります。通勤がなくなり、柔軟な働き方ができる一方で、同僚や上司との距離が広がったと感じることもあります。特に最近気になったのが「解雇の伝え方」です。日本でも少しずつ話題になっていますが、アメリカでは、もはや解雇の知らせを直接伝えないケースが急増しているようです。
誰かが突然チャットにいなくなったり、社内ツールのアクセスが切られたりするのを見かけるたび、「あの人、もしかして……」と胸騒ぎがします。そんななか、最新の調査結果を読み、私の感じていたことが確かな傾向であると実感しました。この記事では、その調査内容をわかりやすくまとめつつ、これからの働き方や心構えについて考えてみたいと思います。
リモートで進む「非対面の解雇通告」
アメリカのキャリア支援企業Zetyによる2025年のレイオフ調査レポートによれば、過去2年以内に解雇された1,000人以上のうち、**対面で通告されたのはわずか30%**にとどまりました。その他は以下の通りです:
- メール通知:29%
- 電話連絡:28%
- ビデオ通話:5%
- 社内の噂から:6%
- システムアクセスの停止で気づいた:2%
直接会っての説明が少ないのは、リモート化が進んでいる影響が大きいですが、社員から見れば不意打ちに感じられることも少なくないでしょう。
解雇の主な理由と社員の受け止め方
レイオフの原因として多く挙げられたのは以下の通りです:
- コスト削減
- 会社の縮小
- 組織再編
- 財務状況の悪化
社員側は多くが自分を責めておらず、53%が「会社の事情が原因」と回答しました。一方で、42%は「自分の業績も一部関係している」と認識しており、**完全に自己責任だと答えた人はわずか5%**にとどまりました。
レイオフの「兆し」に気づいていた人は多い
「解雇は予想外だったか?」という問いに対して:
- まったく予期していなかった:21%
- 薄々感じていた:43%
- 確信していた:36%
予兆を感じていた人が実に8割近くいたことからも、社内の雰囲気や業績などから察する社員が多いことがうかがえます。
退職金の支給状況と会社への信頼感
退職金(セベランスパッケージ)については、74%が「手厚かった」と評価し、**22%が「不十分だった」**と回答、**4%は「まったく支給されなかった」**と答えています。
それでも89%が「解雇の対応は公正だった」と感じており、90%は「将来、元の会社に戻る可能性もある」と答えています。解雇のされ方が丁寧であれば、関係性は断たれないということがわかります。
求人市場の現状と今後の展望
労働市場全体を見ると、2025年3月時点での解雇率は**わずか1%**と、歴史的に見ても低水準にあります。しかし、求人件数は減少傾向にあり、2024年3月の800万件から、2025年3月には720万件へと下がっています(米労働統計局調べ)。
レイオフを乗り越えるための5つの戦略
Toggl HireのCEOでキャリアエキスパートのAlari Aho氏は、「レイオフは個人の価値を決めるものではない」と述べ、以下の5つの戦略を推奨しています:
- 自分の物語をコントロールする
面接やSNSでは、「ビジネス上の判断だった」と位置づけ、得た学びや今後の目標を明確にすることが重要です。 - 自分を再ブランディングする
LinkedInのプロフィールや履歴書を更新し、自分の価値を見える形で発信することが、思わぬチャンスを呼び込むこともあります。 - 人脈を目的意識を持って活用する
単なる求人探しではなく、「こういう仕事を探している」と具体的に伝えることで、周囲の協力も得やすくなります。 - スキルアップに時間を使う
AIやデジタルマーケティングなどの新スキル習得は、競争力を高めるうえで非常に効果的です。 - オンライン上での可視性を高める
業界トレンドへの意見発信や、自身の再出発の過程を共有することで、信頼性と注目度がアップします。
まとめ:リモート時代の「辞め方」は会社の評価にも影響する
解雇はつらい経験ですが、その伝え方や対応の仕方で会社への印象は大きく変わります。リモートワークが主流となった今こそ、「人としての誠意」が試される時代です。そして、解雇された側も、それをきっかけに前向きな転機をつくることができます。私自身もいつ何が起きても動じないよう、心の準備とスキルアップを怠らないようにしたいと感じました。
出典:
- Zety社 2025 Layoff Experience Report
- 米労働統計局(BLS)2025年3月データ
- コメント:Alari Aho氏(Toggl Hire CEO)

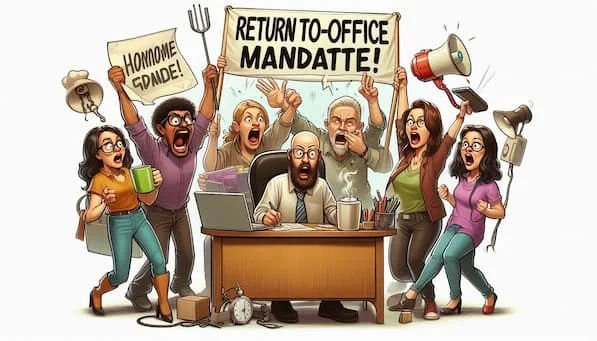

コメント