関税の迷走で、日常も仕事もじわじわと圧迫されていると感じるこの頃
ハワイ・オアフ島で暮らしていると、観光業や物流、さらにはスーパーでの買い物の値段からも、「あれ?最近高くなってない?」と感じることが増えてきました。
私はIT業界にいるので日々の業務がグローバル経済にどう影響されるかを比較的客観的に見ていますが、それでもここ最近のアメリカの関税政策の急展開には正直ついていけない部分もあります。
特に今年2025年に入ってからの動きは目まぐるしく、トランプ大統領による第2期政権下での“関税の乱れ打ち”が企業活動全体に波紋を広げています。関税の発動と一時停止が繰り返されるなかで、企業は価格を引き上げたり、従業員の解雇に踏み切ったりするケースが急増しています。
雇用削減が急増:5月のレイオフ件数は前年比47%増
2025年5月に発表されたChallenger, Gray & Christmas社のレポートによると、アメリカ全体で93,816人がレイオフの対象となり、前年同月比で47%増加しました。
シニアVPのアンドリュー・チャレンジャー氏は次のようにコメントしています:
「関税、予算削減、消費者心理の悪化が重なり、企業の人件費圧力が一気に高まっています」
特に直近では、2025年6月4日から鉄鋼とアルミニウムに対する50%の関税が施行され、これが製造業全体に大きなコスト増をもたらしています。
関税コストを誰が負担する?──企業は価格転嫁を進める
Principal Financialの調査(2025年4月)によれば、中小企業の約51%が価格を引き上げているとのこと。さらに、ニューヨーク連邦準備銀行のレポートによると:
- 製造業者の30%以上が関税コストを全額価格転嫁
- **サービス業者の45%**も同様に価格を引き上げ
- 一方で25%の製造業者はコストを転嫁できず、利益を圧迫されている
こうした背景から、多くの企業が**「価格を上げざるを得ないが、それによって消費者が離れる」**というジレンマを抱えています。
小売・サービス現場でも広がる不安感
労働者側にも影響が出ています。UKG社の調査によると、現場スタッフの52%が解雇を心配しており、74%が関税が将来の収入に影響すると感じていると回答しました。
特にZ世代(1997年以降生まれ)では63%が「職を失うのでは」と懸念しており、ベビーブーマー世代(1946〜1964年生まれ)の28%と比較すると、そのギャップは顕著です。
M&A市場にも冷や水:「まるで市場に原爆を落とされたようだ」
中堅企業の買収・合併(M&A)も、2025年初頭は活発に動いていたものの、予測不能な関税政策の影響で現在は急ブレーキがかかっています。
Moore Colson社のM&A専門家クリストファー・フェイガン氏は、次のように表現しています:
「まるで原爆を市場に落とされたようなものだ。誰もが動けなくなった」
これは、買い手と売り手の双方が将来の収益見通しを立てられなくなっていることが原因で、**「予測できない=リスクが高い」**と判断され、取引件数が急減しています。
中小企業経営者の77%が「関税の不確実性が最大の問題」
Goldman Sachs「10,000 Small Business Voices」調査によると:
- 36%の中小企業がすでに関税の影響を受けている
- 38%が将来的に影響を受けると予想
- 77%が「不確実性」こそが最大の課題と回答
このように、“実際の関税額”よりも、“政策がいつ変わるか分からないこと”こそが最大の問題になっているというのが、今回のニュースの核心です。
ハワイに暮らす私たちへの影響もすぐそこに
ハワイのように物資の大半を本土や海外に依存する地域では、このような関税政策の影響が非常に早く、そして直接的にやってきます。実際、最近のガソリン価格や食料品価格の上昇も、こうした動きと無関係ではないでしょう。
まとめ:不確実性が経済を止める時代に
関税政策そのものが悪というわけではありません。ときに国内産業を守る手段として有効です。ただし、戦略なき関税の乱発は、むしろ企業と消費者の信頼を損ね、経済全体を冷やしてしまう可能性があることが、今回のデータからも明らかです。
特に、長期的に価格設定や採用戦略を立てなければならない中小企業にとっては、「いつ変わるか分からない政策」は最も恐ろしい敵です。
私たち生活者としても、こうした変化に敏感であると同時に、情報を正しく捉え、将来に向けての備えを怠らないことが求められています。

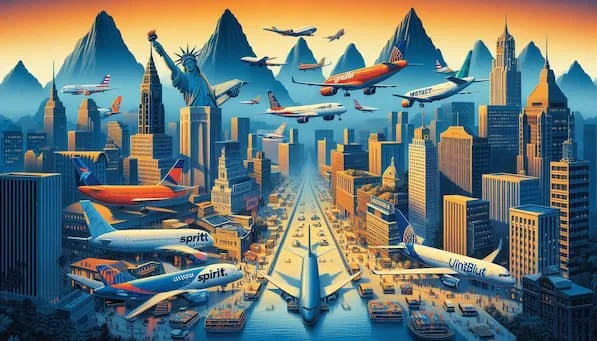

コメント